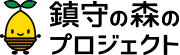鎮守(ちんじゅ)の森のプロジェクトのボランティアに参加する
森づくりはたくさんの人手と継続的なボランティアを要します。
「地域と暮らしを守る防災の森」づくりに参加しませんか。
鎮守の森のプロジェクトでは植樹だけでなく、育樹(森を育てる)や採種(森となる種を拾う)など、
四季に合った継続的なボランティアがあります。
ボランティアメールに登録すると、活動のご案内を随時メールで配信します。
また、当財団で募集するボランティア活動では、「ボランティア活動参加証明書」も発行しています。発行までの手順はこちらから。
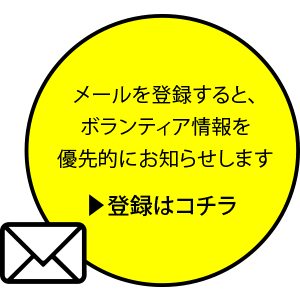
活動サイクルとボランティア
鎮守の森のプロジェクトの活動には年間を通して次のような流れがあります。種子となるどんぐりを拾うこと(採種)、拾ったどんぐりから発芽させて苗木にするまで育てること(育苗)、育った苗木を植えること(植樹)、植えた苗木が森として育つまで草抜きなどの手入れをすること(育樹)。これらの活動にはたくさんのボランティアの人手が必要です。私たちと一緒に、「地域と暮らしを守る森」をつくりませんか。

☆2024年ボランティア募集予定(見込み)はこちらからご覧ください。
静岡県磐田市|市制施行20周年・海岸防災林植樹祭2026〜いのちを守る森の防潮堤〜
東日本大震災の教訓を受け、静岡県磐田市では、津波からいのちを守るための新たな海岸防災のかたちとして、「森の防潮堤」づくりに取り組んできました。
この取組みは、地域本来の自然の力(潜在自然植生)と、先人の知恵、そして地域の人々の力を生かし、津波や強風、飛砂などの被害を軽減する、多重防御を担う海岸防災林を育てていくものです。皆さまのご参加を、心よりお待ちしています。

開催概要(雨天決行・荒天延期)
| 日程 | 2026年3月21日(土) |
|---|---|
| 時間 | 13:30〜15:30終了予定(受付は13:00〜) |
| 植樹本数 | 4,000本 |
| 募集人数 | 400名 |
| 場所 | 塩新田地内海岸防災林 |
| 主催 | 磐田市/共催 鎮守の森のプロジェクト |
| 持ち物 | 汚れてもよい服と靴(雨天や雨天翌日は長靴がおすすめ)、帽子、リュックサック(両手で作業できるもの)、軍手、雨具、タオル、飲み物(水分補給用)、園芸用移植ゴテ(ある方) |
| アクセス | 下記の①か②の方法でお越し下さい。 ①送迎シャトルバスに乗る【事前申込】 【往路】先発12:10、後発12:30/JR磐田駅南口ロータリー発(片道20分・赤色のバスを目印にご乗車ください・バスには市のマスコットキャラクターしっぺいが描かれています。) → 植樹地バス発着所(植樹会場まで徒歩15分程度・約1km。会場までのルートは②の会場近郊地図をご参照ください。) 【復路】植樹祭終了後3便運行、15:30、15:45、16:30最終/下車地発→ JR磐田駅南口 ※時間は目安です。 ②自家用車で行く 駐車場:鮫島海岸駐車場をご利用ください。 ※「浜松シーサイドゴルフクラブ:静岡県磐田市鮫島4119−1」を目指してお越しいただき、ゴルフ場施設を超えて、海岸突き当たり左側に駐車場スペースをご用意します。駐車の際は、誘導員に従って駐車してください。※駐車場から植樹会場まで徒歩10分程度(約600m程度)。会場に到着後は、受付テントにお立ち寄りください。植樹する区画のご案内をいたします。 |
| 特記 | ※荒天による中止連絡は前日正午までに、同ページとお申込メールへお知らせします。 |